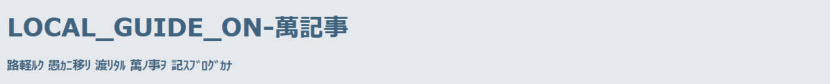TOP 1 From http://localguidyorozukiji.seesaa.net/ アーカイブ blog URL
2010年に、35年間の行政職歴で行政手続の法務専門職の行政書士事務所を登録開業。「ホームページ」と、「ブログ」・「デジタルブック」サイトも開設。2015年には個人資産相談業務検定資格ファイナンシャルプランナーとして相続・不動産管理運用支援も。しかし、サイト更新やリンク編集の維持が難しくなり、ウエブサイトを整理して最終的に、リンクブログも選別アーカイブサイトにしました。
COPYRIGHT(C)2010 木嶋行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED URL http://gykijima.client.jp/
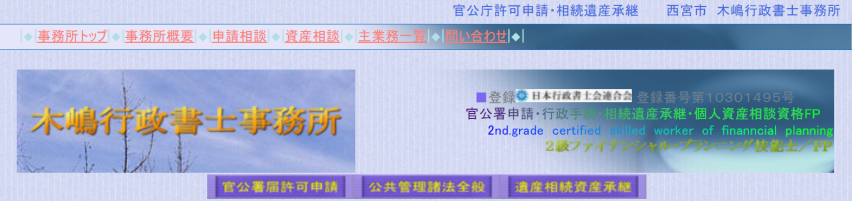
2014 / 2019 / 2020 / 2021〜 ブログ セレクト アーカイブ 「1」 年金考察 〜 入院/ブログ終了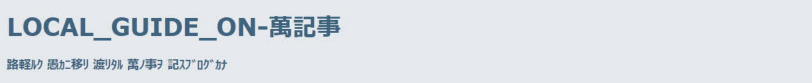 |
2020年10月21日 「街の総合病院にて」
2019年2月に久々のブログ更新。それから、1年8ヶ月。ウエブサイトの整理の方向へ。
その転機となった「街の総合病院にて」。
2年半前、街の総合病院へ救急外来受診。
高額検査、専門医不在、手術治療と投薬副作を身をもって経験。
2017年7月以来の口腔外科感染症再発。2018年3月、耳鼻咽喉科に発熱と顔面炎症発症受診。
個人医院対応不可で、紹介状を持たされ街の総合病院の救急外来へ。
時間外の総合病院では救急診療の前に外来受付に。
当直医が内科のみで、耳鼻咽喉科医師不在の為、抗生物質の点滴と後日再来院の指示のみ。
翌日再受診では当直内科医の指示が継続され、
またも抗生物質の点滴が3日連続。症状は改善せず耳鼻咽喉科は検査のみ。
4日後、耳鼻咽喉科主治医から口腔外科に院内転科。
口腔外科では緊急手術で、副鼻腔に充満していた感染症由来の膿を除去。
口腔外科部長曰く、「点滴を4回も繰り返しても病巣の膿を除去しないと炎症は直らない。」との事。
そして翌月4月、耳鼻咽喉科で歯性副鼻腔炎の手術入院。既に口腔外科で緊急処置の副鼻腔炎。
さらに半年後の10月に、口腔歯性感染症由来の耳下腺腫瘍摘出手術入院。
翌年2019年3月、やっと総合病院での耳鼻咽喉科検査治療が終了。
同年4月に口腔外科の急性期治療終了。翌月他の口腔外科歯科医院に転院し感染症治療継続。
2018年3月当初、総合病院内科で炎症と高熱の急性期に血液検査数値項目が複数悪化。
腎臓・膵臓の投影CT/MRI/血糖値等毎月検査に大量投薬治療1年1ヶ月、血糖値は2型範疇に。
2019年4月まで毎月、急性期薬量でビグアナイド先発薬とDDP4薬を継続処方され、
極度の倦怠感と筋肉痛が増幅。歩くのもままならない程の投薬副作用(乳酸アシドーシス)の進行。
毎月院内で半日検査を要して問診処方は3分。更に1年1ヶ月の間に内科外勤医が3人も交代。
2回の入院手術と、高額の毎月検査と全く同一の院内処方の投薬が1年続いた結果、
筋肉痛と体調不良が進行、仕事の大半と、毎週のスポーツや、他のボランティアも、活動停止に。
ついに、
2019年5月に別の内科医院に転院し、歯性感染症手術と後遺症から2年目にして、
内科クリニックの管理栄養士の食事制限指導や、リハビリ運動と、適切な薬処方にて、
徐々に検査値と副作用も改善。
口腔外科医では、転院後複数回感染症治療処置継続中。
結論、「もう大量検査に大量投薬と副作用で、専門医不在の街の総合病院には行かない。」
2019年02月05日 「はて、年金世代に働くとは?」
2014年6月以降4年7ヶ月のブログ空白期間。ブログの継続には時間と体力が要ります。
と言うことは、それなりの理由が有って、ブログ放置に。
さて、今や会社の事情で非正規でも、アルバイト雇用でも、65才まで働き続けなければならない時代に。
団塊の世代以前の昔は60才で定年、即満額の厚生年金を受給し、
後期高齢者に至っても悠々自適の年金生活が保証されて、今の現役世代とは何という待遇格差でしょう。
ところが、団塊の世代後の、働かないといけない立場の自分自身が、
2014年以降、急遽の生計維持の必要から本業の法務専門職と掛け持ちでの外勤バイトの無理が祟り、
2017年7月以降、高熱と体調不良に陥り、
遂に、追い打ちを掛けるように、2018年4月に、歯性副鼻腔炎手術入院。
2018年10月に、歯性耳下腺腫瘍手術入院。以降、生活の大半は療養。たまに仕事の有様に。
中高年が何とか苦労して仕事をしても、健康問題が高齢就労の大きなリスクになります。
一旦、長期療養になれば休職や離職に。
自身のブログで、就職・年金・役所の問題に取り組んできたのも今は昔の事に。
2014年以降、自分自身や家族も健康問題や景気の荒波に翻弄されることに。
結果、中高年起業活動に無理な仕事も祟り、ついには入院通院の日々でブログはお休み。
気がつけば、65歳を過ぎ、年金受給世代へ。減額改正されても、無くては困る年金。
経験して初めて解る減額改正年金。 「はて、年金世代に働くとは?・・・!」
2014年06月29日 「やっぱり下がる!年金試算」
やっぱり下がる!年金試算厚生年金:「現役世代の50%」 受給開始直後のみ 厚労省試算
[毎日新聞 2014年06月28日 東京朝刊]
厚生労働省は27日の社会保障審議会年金部会(厚労相の諮問機関)に、
モデル世帯の厚生年金の給付水準(現役世代の平均的手取り額に対する年金額の割合)が、
受給開始から年を取るにつれてどう変わるかの試算結果を年齢層別に説明した。
ともに1979年度生まれで現在35歳の夫婦の給付水準は、
受給を始める65歳(2044年度)時点では50・6%あるものの、
受給期間が長くなるほど低下し、85歳以降は40・4%まで下がる。
どの世代をとっても受給開始時は50〜60%台の水準ながら、
90歳付近になると41・8〜40・4%まで低下する。
政府はモデル世帯(平均手取り月額34万8000円の会社員の夫と専業主婦の妻、
夫婦は同じ年齢)の夫婦2人分の年金給付水準について、「50%を維持する」と法律に明記。
6月3日に公表した、5年に1度の公的年金の検証結果でも、2015年度から2043年度まで
労働人口の減少などに応じて毎年、年金を1%程度カットする仕組み(マクロ経済スライド)を導入し、
14年度の給付水準(62・7%)をじわじわ下げていけば、
2043年度以降は50・6%を維持できるとしていた。
しかし、今回の追加試算で、「50%」は受給開始時の話に過ぎないことが明確になった。
試算はいずれも、将来の実質賃金上昇率が1・3%で推移することなどを前提としている。
年金の給付水準は、もらい始めは現役の賃金水準に応じて決まり、
受給開始後は毎年、物価の動きに合わせて増減されるのが基本。
通常、物価(年金)の伸びは賃金の伸びを下回るため、年金は賃金の伸びに追いつけず、
現役の賃金に対する年金額の割合を示す給付水準は、年々低下する。
2015年度から2043年度までは、マクロ経済スライドの適用を前提としている。
この間の年金の伸びは物価上昇率よりも低く抑えられる。
その結果、
2014年度に65歳で受給を始める1949年度生まれの夫婦は、最初の給付水準こそ62・7%だが、
2019年度(70歳)は58・1%、2024年度(75歳)は51・6%と年々下がり、
2039年度(90歳)には41・8%に低下する。
若い世代はさらに厳しい。1984年度生まれの30歳の夫婦の場合、
2049年度(65歳)の受給開始時に既に50・6%。5年後には47・4%と5割を切り、
2069年度(85歳)には40・4%となる。
こう言う試算は 何故 後から追加発表されるのでしょう。
正規雇用前提のモデル年金でもやっぱり年金は下がる。
1900万人以上いる非正規雇用者の年金試算はどうなるのでしょうか。
2014年06月24日 「ほんと大丈夫?老後の年金」
ほんと大丈夫?老後の年金 国民年金:免除申請勧奨も影響…
納付率回復 [毎日新聞 2014年06月23日]
厚生労働省は23日、国民年金の保険料納付率が2013年度は20代を中心に改善し、
全体では前年度を1.9ポイント上回る60.9%になったと発表した。
景気の回復に加え、年金記録問題が一段落し、
日本年金機構の職員を保険料徴収に振り向けられるようになり
若者を中心に保険料の免除申請を勧めたことも影響したようだ。
免除を受けると無年金にはならない半面、納付するよりは年金額が低くなる。
免除者の増加は将来、低年金に陥る人が増えることにつながる。
国民年金保険料の納付率は、1976年度に96.4%まで伸びたものの、
近年は低迷し、11年度は過去最低の58.6%に低下した。
その後2年連続で上昇し、13年度は08年度(62.1%)以来、5年ぶりに60%台に回復した。
世代別にみても、13年度は全年代層(5歳刻み)で前年度を上回った。
特に20〜24歳(56.3%)は5ポイント上昇し、25〜29歳(49.9%)も3.1ポイント改善した。
地域別でも全都道府県で改善した。ただ、改善の原因は滞納対策の強化だけでなく、
生活が苦しい若者らに保険料免除を申請するよう働きかけたことにもあるようだ。
免除を受けると未納とはみなされず、これまで未納だった人が免除を受けると、
見かけ上納付率はアップする。
13年度、納付義務がある人は1805万人と前年度より58万人減る一方で、
免除などを受けている人は19万人増の606万人と、全体の3分の1を占めるようになった。
原則、未納の間は年金の受給資格期間(25年、15年10月から10年)に数えられないのに対し、
免除されている間は受給資格期間にカウントされる。
免除期間に対応する将来の年金は、税金から本来の半額が支給される。
それでも、国民年金は満額でも月約6万4000円。減額されると老後の支えとするには相当厳しい。
そうした中、厚労省は16年7月から、現在30歳未満にしか認めていない
納付猶予制度の対象を50歳未満まで広げる。
猶予期間は受給資格期間には数えられるが、年金額には反映されない。
保険料を追納できないまま老後を迎える人が多くなると、さらに低年金の人が増える可能性もある
さて その低年金だが、20歳から60歳までの40年間
保険料(平成26年度は月額15.250円)を支払い続けて現行65歳から、満額の年間772.800円
最低期間の25年間払って 25/40で 年483.000円 月40.250円の年金である
しかも 全額免除期間は二分の一になる。
来年から 受給資格期間を10年にしたら 年額193.200円 月16.100円にしかならない
これでは 老後の支えには不足だ。 とにかく元気に65歳まで働くしか仕方ない。
更に、厚生年金:給付水準50%試算、成長頼み[毎日新聞 2014年06月03日]くらしナビ・ライフスタイル:
年金財政検証から/加入者増で「底上げ」検討[毎日新聞 2014年06月18日 東京朝刊]
公的年金が維持できるかどうかを5年に1度点検する「年金財政検証」(今月3日公表)について
厚生年金の加入者を増やして年金額も増やそうとする案が盛り込まれました。
「週20時間」条件に厚生労働省は、「モデル世帯」(平均的な収入の夫と専業主婦の妻)の場合、
厚生年金については将来とも
現役男性の平均的手取りの半分となる「50・6%」の給付水準で受け取れるとしています。
ただ雇われて働く人の中には、パートや非正規雇用が増えています。
こうした人は厚生年金加入の条件に満たない場合、国民年金に入ることになるため
国民年金加入者の3割はパート・非正規の人になっています。
厚労省は より手厚い厚生年金(平均的なサラリーマン1人分で月15万円程度)に
入ることができる人を増やすとともに、厚生年金自体の底上げも検討し
既に厚生年金の加入者を増やすための条件拡大が一部決められています。
現行制度では
「1週間に30時間以上」働く必要がありますが、2012年の「税と社会保障の一体改革」によって、
16年10月からは「週20時間以上」「従業員501人以上」の企業で働き、
「月収8万8000円以上(年収約105万円以上)」の人約25万人が
新たに厚生年金に入ることが既に決まっています。
ただ、それでも厚生年金に未加入の雇用者(約1500万人)の2%弱に過ぎません。
そこで同省は、さらに加入者を増やす案を今回示しました。
労働時間は週20時間以上で変わりませんが、
収入の条件を「月収5万8000円以上(年収約70万円以上)」に下げ、
「従業員500人以下」の企業にも広げる案で、
国民年金に加入する非正規雇用者ら約80万人が厚生年金に移ると見込む。
また、年収を130万円未満に抑えて夫の扶養を受け、
保険料を払っていないパートの主婦ら約100万人なども加わり、
厚生年金への新規加入者は計220万人になると想定。
加入者が増加すれば保険料収入が増え、
モデル世帯の給付水準は0・5ポイント増の「51・1%」に上昇すると見込む。
これとは別に同省は、労働時間に関係なく、「月収5万8000円以上」の未加入者全員を
厚生年金に迎え入れた場合も試算しています。
対象者は学生も含め、フルタイムで働く600万人、パートの600万人の計1200万人で、
これだけ増えれば給付水準はもっと改善され、6・9ポイント増の「57・5%」になる試算。
しかし、厚生年金の保険料は企業側が半分を払わねばならず、
企業には新たな保険料負担が生じます。
スーパーや外食産業などパートの比率が高い業界は反対する構えで、
対象者をどれだけ広げられるかは見通せません。
はて結局
試算はただの試算で更に、65歳以降も働いて厚生年金に加入し、「納付期間延長」案も提示
年金を増やすためのもう一つの案として
厚労省は、国民年金(基礎年金)の加入期間(現在20歳から60歳になるまで)を5年延ばし
その間も働いて65歳以降も厚生年金に入り、受給開始年齢(原則65歳)を遅らせる案も示しました。
加入期間を65歳まで延ばす案の場合、
給付水準は6・5ポイント改善し「57・1%」に上昇すると試算。
60歳以降も保険料を払う人が増え、その分財源にゆとりが生まれるからです。
また、受給開始年齢を遅らせると、
年金を受け取るまで働いて厚生年金に入る場合はさらに給付水準が上がります。
払い込む保険料が増えるほか、受給開始年齢を1カ月遅らせると
年金額は0・7%ずつ増える仕組みがあるからです。
67歳まで2年繰り下げると給付水準は「68・2%」に、70歳なら「85・4%」と、
受給開始を遅らせるほど年金は増える計算です。
ただし、受給開始を70歳まで繰り下げる場合、
受け取る年金の総額が65歳から受給し始めるのと同じ金額になるのは、
約12年後、82歳になるころです。
結局 現在20歳から30歳の約半数だけの国民年金支払者では足らずに
アルバイト パート主婦などの非正規労働者も厚生年金に加入させる案であり、
しかも退職した者は65歳まで保険料を支払うことに。
年金はいつになったら受給できるのか?
そう
試算では70歳から受給して 82歳時にやっと本来額に並ぶとは!
あまり 現実的な計算ではありませんね
例え非正規でも現行65歳 更に70歳まで会社で働き続けているなんて
その内 平均余命まで働いて 年金はそれから なんてことには ならないですよね
COPYRIGHT(C)2020 木嶋行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED